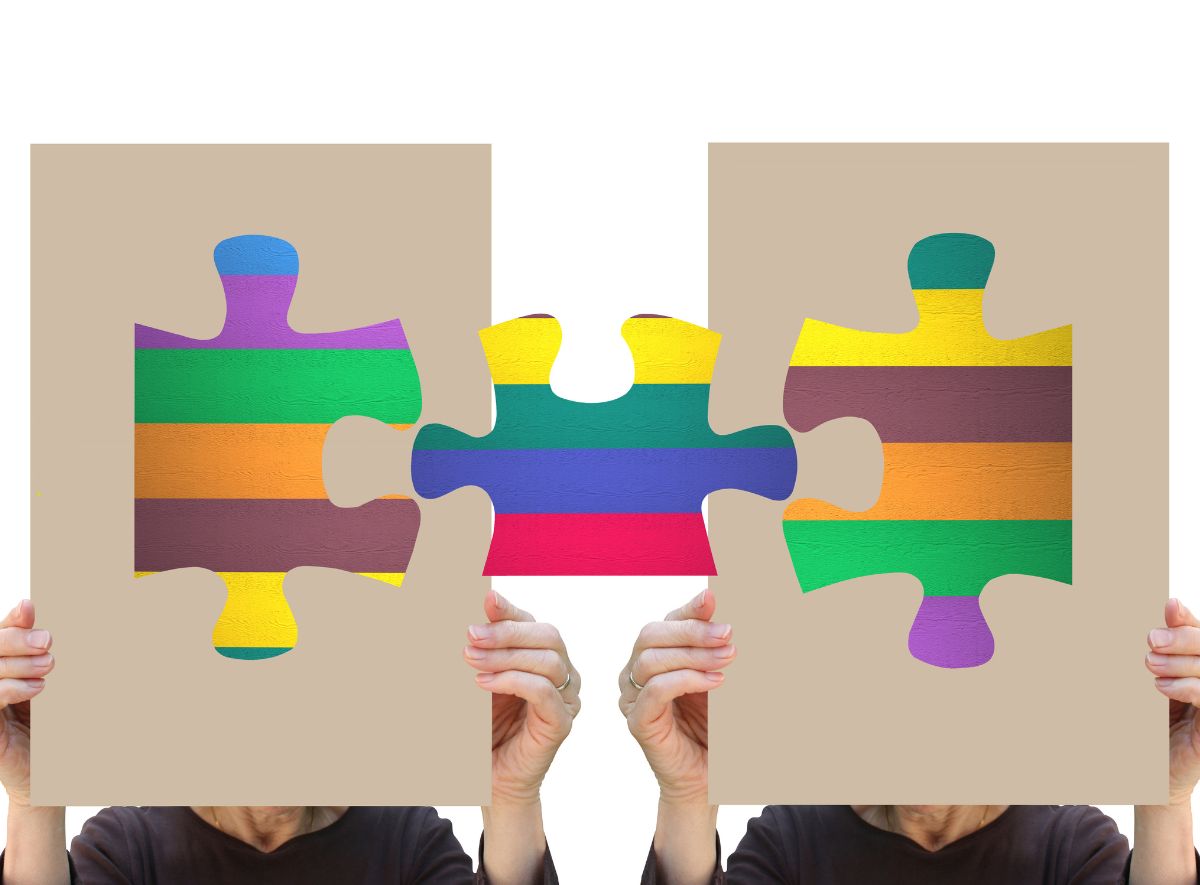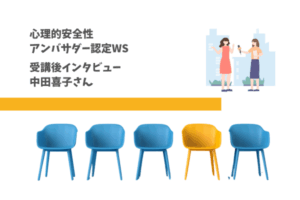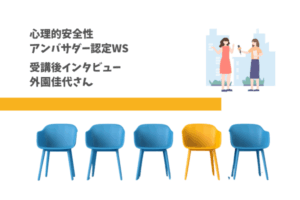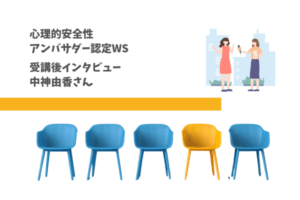小さな実践から広がる心理的安全性
今回のブログは、心理的安全性アンバサダーであり、病院で勤務されている Nさん(のんちゃん)にインタビューしました。
心理的安全性は、特別なプログラムや大改革ではなく、日常の小さな工夫から育まれます。
チームでの問題解決、面談での学び、そして「放課後」に象徴される自然な関わりまで――。心理的安全性が現場でどう生まれ、広がっていったのかをお伝えします。
ゲストスピーカー:心理的安全性アンバサダー Nさん(のんちゃん)
インタビュアー:心理的安全性アンバサダー協会 代表理事 横内浩樹(ひろき)

医療福祉法人で見えた課題
ひろき:
私が医療福祉法人を心理的安全性研修で訪問したときの話です。現場のお話から「変化を嫌う空気」があると聞きしました。新しい学びの必要性は理解されているのに、一歩踏み出せない。
のんちゃん:
ああ、それは分かります。現場では「これまで通り」が一番安心ですからね。
ひろき:
そういいう意味では、のんちゃんが病院で実施している取り組みが、チームの変化を自然と促す素晴らしい取り組みだと思っています。
チームで対話をしながら進める
ひろき:
チームで対話しながら業務を進めていくお話をお聞きしても良いですか?
のんちゃん:
私が他部署の課長になったときのことです。「自分たちの仕事は自分たちで考えてもらう」ことを大切にしました。ちょうどコロナ禍で、送迎を自分たちですることで経費削減することが課題となりました。
ひろき:
そこでチームをつくり、対話しながら進めるやり方が始まったわけですね?
のんちゃん:
はい。そこで3〜4人のチームをつくり、対話しながら問題解決に取り組んでもらいました。トライアンドエラーを繰り返すうちに工夫が生まれ、最終的には自分たちで送迎を回せるようになり、1000万円の経費削減にもつながったんです。今も人手不足の中で回せているのは、この仕組みのおかげです。
ひろき:
チームで対話しながら、問題解決していくのはまさに心理的安全性で言うところの学習する組織ですよね。
のんちゃん:
そうですね!新しく入った職員が「ここの病院、みんなで話しながら決めていくんだよ!」と話しているのを聞いたこともあります。
ひろき:
確かにビックリするかもしれませんね。言われたことをやるだけではなく、課題に対してチームで話し合って決めていくわけですもんね!
心理的安全性アンバサダーを受講して良かったこと
ひろき:
心理的安全性アンバサダーを受講された後に面談がスムーズに進むようになったとお聞きしました。
のんちゃん:
はい。面談シートを渡されても、欄を埋められず形式的になってしまいました。でも心理的安全性アンバサダー講座を受けて、「同じイメージを見ながら話をすること」の大切さを学んでからは、自然に会話が広がり、欄も埋まるようになったんです。
ひろき:
共通のイメージを持つだけで、対話の質がぐっと変わるんですね。心理的安全性アンバサダーで学んだことを活用して頂けてとても嬉しいです(^^)
Nさんの放課後
ひろき:
普段の関わりの中でも、心理的安全性を感じる場面はありますか?
のんちゃん:
ありますよ。私が帰ろうとすると、「ちょっと話したいんです」と職員が自然と集まってきて、おしゃべりが始まるんです。職員たちはそれを「Nさんの放課後」って呼んでいます(笑)
ひろき:
それは素敵ですね!自然と人が集まるのは、安心して話せる雰囲気があるから。心理的安全性の象徴だと思います。私も聞いていてとても温かい気持ちになりました。
話しやすい雰囲気をつくる工夫
ひろき:
業務の中で、のんちゃんはどんな実践をされていますか?
のんちゃん:
まず「話しやすい雰囲気づくり」を意識しています。朝の打ち合わせでは必ず「一言スモールトーク」を入れるんです。「昨日こんなことがあって…」とか「今日はこんな気分です」みたいに。
ひろき:
なるほど。いきなり業務ではなく、ちょっとした雑談から入るんですね。
のんちゃん:
そうです。それだけで場が柔らかくなり、発言のしやすさが変わります。それに、部下の提案はできるだけ「Yes, And」で受け止めています。「いいね、そしてこうしてみたらどう?」と返すことで、「話してよかった」と思ってもらえるようにしたいんです。
ひろき:
素晴らしいですね!肯定から入り、意見を付け加える積み重ねが、共感している姿勢も伝えることができて心理的安全性をつくりますね。
小さな実践の積み重ね
ひろき:
のんちゃんとのお話を聞いていると、「チームで対話しながら進める」仕組みづくりと、日々の会話のなかでの関係性づくりをされているのが心理的安全性につながっていると感じました。
のんちゃん:
そうですね。現場では「小さなこと」からでないと続きません。提案を受け止める、雑談を欠かさない――そんな積み重ねが変化を嫌う空気をやわらげます。
ひろき:
小さなYes, Andの積み重ねで安心できる環境ができ、そこから学びや挑戦が生まれるんですね。
組織全体に広げる
ひろき:
今では他の部署でも同じことをやってほしいと頼まれ、他部署の管理職も兼任されているとお聞きしました。
のんちゃん:
はい、副部長として部署をまたいで兼任しています。部署を超えて心理的安全性が根付けば、現場全体の学びも深まると思います。
ひろき:
現場全体に心理的安全性が広がり、学びが深められる環境がつくれるととても良いですね。
のんちゃん 本日はご対談いただきありがとうございました(^^)
まとめ
のんちゃんのお話を伺って、現場の変化を進めていくためには大きな改革ではなく、日常の「小さな実践の積み重ね」が大切なのだと改めて感じました。
スモールトークや「Yes, And」での受け止めは心理的安全性を育む土台になりますし、面談でも「同じイメージを共有しながら聴く」工夫が、心理的安全性につながることを実感しました。
また、「Nさんの放課後」と呼ばれる自然な雑談の場が、心理的安全性を象徴する実践として息づいているのも印象的でした。
こうした取り組みが部署を超えて広がることで、組織全体の文化変容につながっていくのだと感じました。

ここまでお読みいただきありがとうございます。
協会では、教育・企業・医療などさまざまな現場で心理的安全性を広める活動を行っています。
詳しい内容やご質問については、下記のお問い合わせフォームをご覧ください。